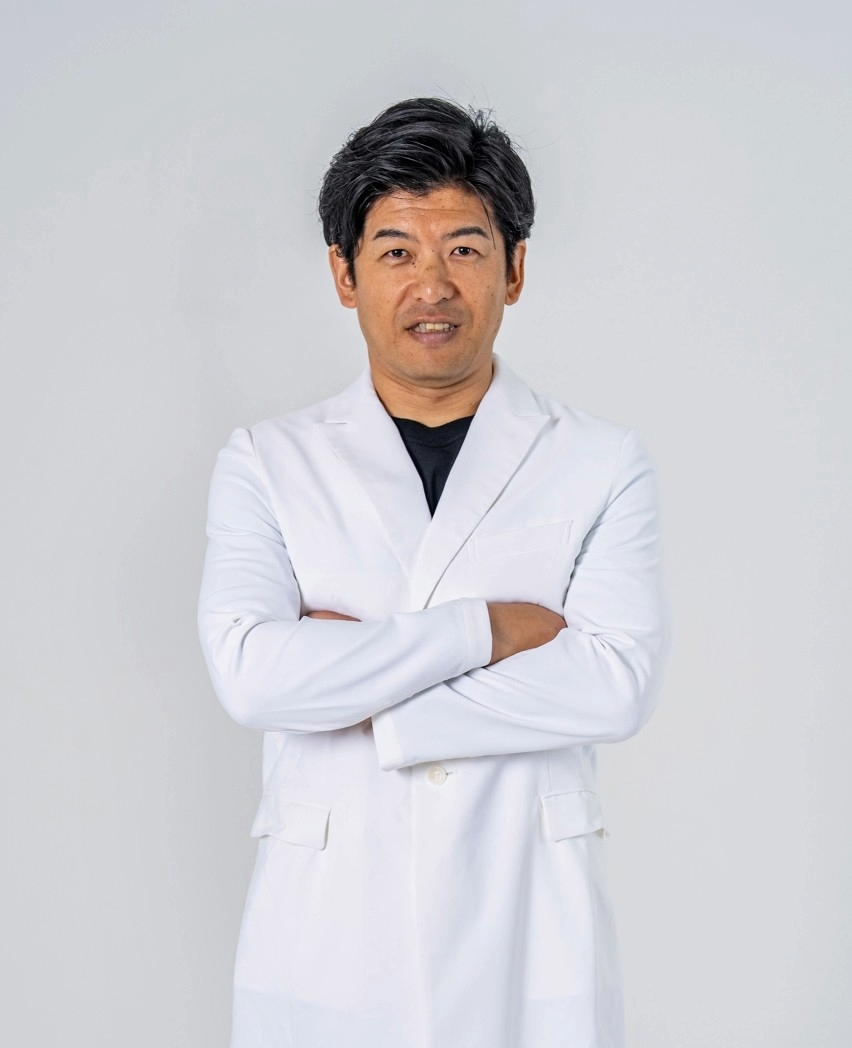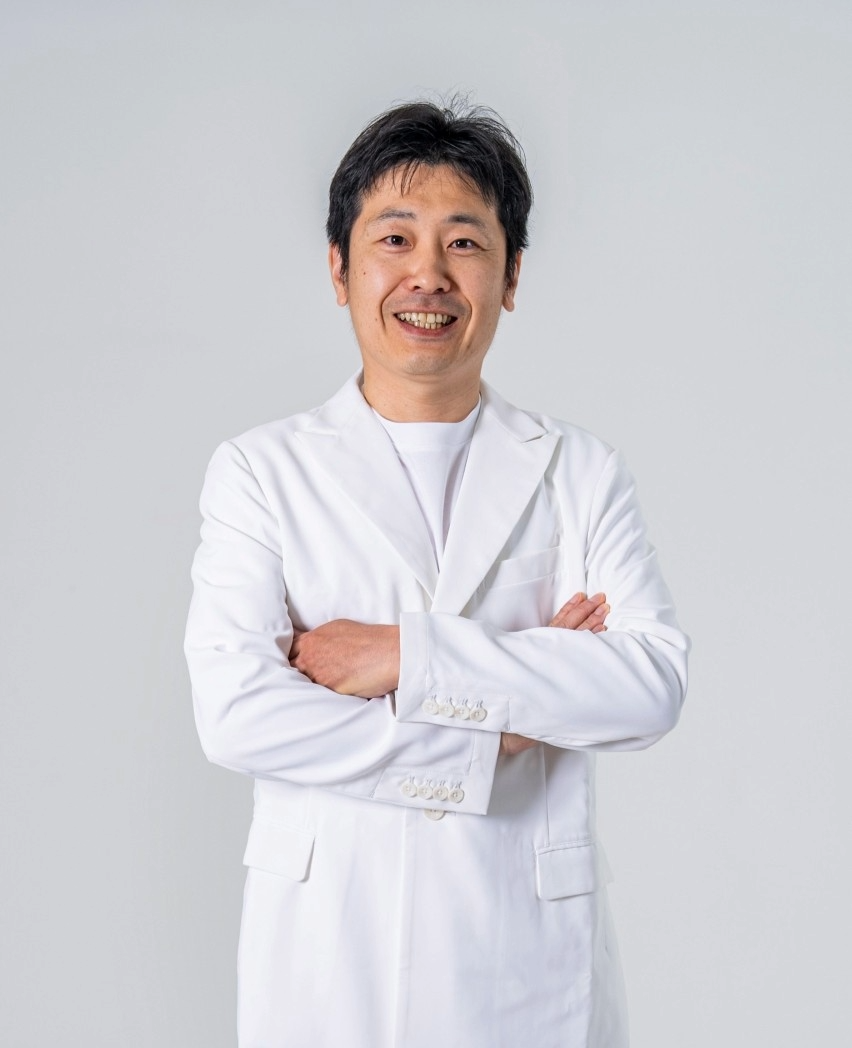ゲノムとは、生物が持つ遺伝子の全体を指す言葉。元々、ゲノムの安定性を保つために修復機構が備わっているが、様々な要因からゲノムのコピー時にエラーが起こったり、酸化ストレスなどの影響で、DNA修復機能は低下しゲノムが不安定になっていくことで、老化が促進される。
老化制御における
サイエンスを
日常へ
老化制御の研究に特化した
NOMON & Co.のサイエンスラボ


NOMON & Co. Science Lab では、
老化制御における様々な最先端科学から
新しいブランド・商品・サービスを創出し、
日常に浸透させていきます。

老化研究と
老化制御のトータル
ソリューションの開発
NOMON & Co.を支える老化の研究や開発業務は、
サイエンティストによって行われています。
世界中の老化研究の元となっているAGING HALLMARKSを指標に、
老化制御のソリューションの提供を行っています。
研究開発を支える、
NOMON & Co.のサイエンティスト

最先端科学で
解明されている
12種類の老化要因

現代の最先端科学で解明されている老化要因のすべてが
AGING HALLMARKS内に明記されており、「12種類の要因」で構成されています。
世界の老化研究において老化現象の根本的な原因や
進行メカニズムを理解するための指標となっており、
老化を抑制したり、治療的な介入の起点となったりしています。
AGING HALLMARKS
3カテゴリー/12種類の
老化要因とは
 プライマリー
プライマリー
防御センサーに
ダメージを与えるもの

- 老化の基本的な(根源的な)プロセスや変化のこと。
- 老化プロセスの起点となる。
- 老化に関連したさまざまな側面に影響を及ぼす。
-
ゲノム不安定性
Genomic instability -
テロメアの短縮
Telomere attrition -
エピジェネティックな変化
Epigenetic alterations -
タンパク質恒常性の
喪失
Loss of proteostasis -
オートファジーの
機能低下
Impaired autophagy
テロメアとは、細胞における寿命時計と言われており、ゲノムが束になって集まっている染色体の末端部に存在している。染色体は細胞分裂しながら新しい細胞をつくりゲノム情報を伝えていくが、分裂される際に染色体の末端から短くなるという性質があり、その末端があらかじめ長くなっている部分がテロメアである。テロメアは染色体が細胞分裂し増殖する度に短くなっていき、細胞分裂の機能が衰え老化が促進される。
近年、DNAの配列が同一であっても、細胞や個人の形質を変化させる機構があることが判明。DNAの配列に依存せず、細胞の種類や環境に応じ、後天的に細胞分裂を経て引き継がれる遺伝子機能の変化や仕組みをエピジェネティクス(epigenetics)と呼ぶ。様々な要因から、エピジェネティックな変化(後天的な遺伝子の変化)が起きることで、細胞の機能が変化していき、老化が促進される。

喪失
Loss of proteostasis
タンパク質は、複数のアミノ酸が1本に繋がった状態で構成され、立体構造を取っている。古くなったり、壊れたりすることで異常なタンパク質となるが、細胞自体がそれを取り除く仕組みを持っている。しかし、老化によりその機能が低下することで、細胞内外に異常なタンパク質が蓄積していく。その異常なタンパク質が、感染症のように正常なタンパク質を侵食していき老化が促進する。
 アンタゴニスティック
アンタゴニスティック
ダメージに関する防御反応

- 老化の進行を抑制し、寿命を延ばす要因を指す。
- 老化によって引き起こされる損傷やストレスに対抗するメカニズムを活性化することで、寿命を延ばす効果を持つ。
-
栄養感知の異常
Deregulated nutrient sensing -
ミトコンドリアの
機能異常
Mitochondrial dysfunction -
細胞老化
Cellular senescence
生物は、身体に適切な量の栄養を確実に摂取するために複数の栄養感知経路に依存している。しかし細胞機能ダメージは、栄養感知経路の制御を不全にし、その結果、間違った方向へ導かれ、身体が実際に食物を必要としないときでも、より多く食物摂取をするためのシグナルを送ってしまうことで老化が促進し、様々な疾患を引き起こす。ちなみに、今のところヒトの寿命延長対策として証明されているのは、断続的なカロリー制限(すなわち断食)のみとされる。
ミトコンドリアは、ほとんど全ての生物の細胞の中に存在し、エネルギー供給源となっている。また、酸化ストレスやカルシウム調節、細胞死の制御、糖・脂肪酸・アミノ酸の各種代謝、免疫反応にも関連しており、細胞の恒常性維持にとても重要とされているので、ミトコンドリアが効率的に働かなくなると細胞機能が低下し、老化が促進する。
細胞は、がん細胞にならないように自分自身で増殖をストップさせるブレーキ機構を有している。がん細胞にならないように細胞増殖を止めた細胞は老化細胞と呼ばれ、この老化細胞が加齢に伴い身体の各組織で蓄積していくことで、老化が促進する。老化細胞は免疫系による細胞除去機能から逃れるような性質があり、歳と共に身体に蓄積していく。老化細胞は蓄積することで組織の機能低下を引き起こすだけでなく、周囲の正常組織に悪影響を及ぼすことが知られている。
 インテグレイティブ
インテグレイティブ
防御反応の限界を超えた場合に発現

- さまざまな老化プロセスやホールマークが相互に関連し、複合的な影響を及ぼすことを指す。
- 老化の複雑さを反映しており、相互に関連しながら老化の進行を加速する可能性がある。
-
幹細胞の枯渇
Stem cell exhaustion -
細胞間
コミュニケーション
Altered intercellular
communication -
慢性炎症
Chronic inflammation -
腸内細菌叢の変化
Dysbiosis
幹細胞は、新しい皮膚を生み出したり、血液細胞を作ったり、骨を作ったり、組織を新陳代謝させる役割を担っている。増殖を繰り返す細胞であるため、老化の影響を受けやすく、老化してしまうと幹細胞が持つ組織を新陳代謝させる力が弱くなり、老化が促進される。

コミュニケーション
Altered intercellular
communication
多細胞生物は多くの種類に分化した細胞から成り立ち、細胞同士のコミュニケーションによって恒常性が保たれ、個体として統率された生物になっている。細胞間の情報伝達には神経による電気的シグナルやホルモンなど液性因子による伝達方法のほかに、細胞同士の細胞質が直接つながるギャップジャンクションを介した伝達方法があるが、多様な要因から細胞同士の情報伝達が乱れると、組織の調和や機能が低下し、老化が促進される。
加齢に伴う免疫系自体の変化(免疫老化)、組織の変化や全身的な代謝や内分泌系の変化など、多様な要因が複雑に絡み合って、慢性炎症が起きやすくなり、老化が促進される。免疫老化は、免疫系の正確性と効率を低下させ、獲得免疫系の低下をもたらすだけでなく、慢性炎症も起こりやすくする。

Dysbiosis
腸内の健康な細菌のバランスが崩れ、有害な細菌が増加し、有益な細菌が減少することで、持続的な炎症反応が生じ、組織や細胞が損傷を受け、老化が進行する。
 AGING HALLMARKSの
AGING HALLMARKSの
成り立ち
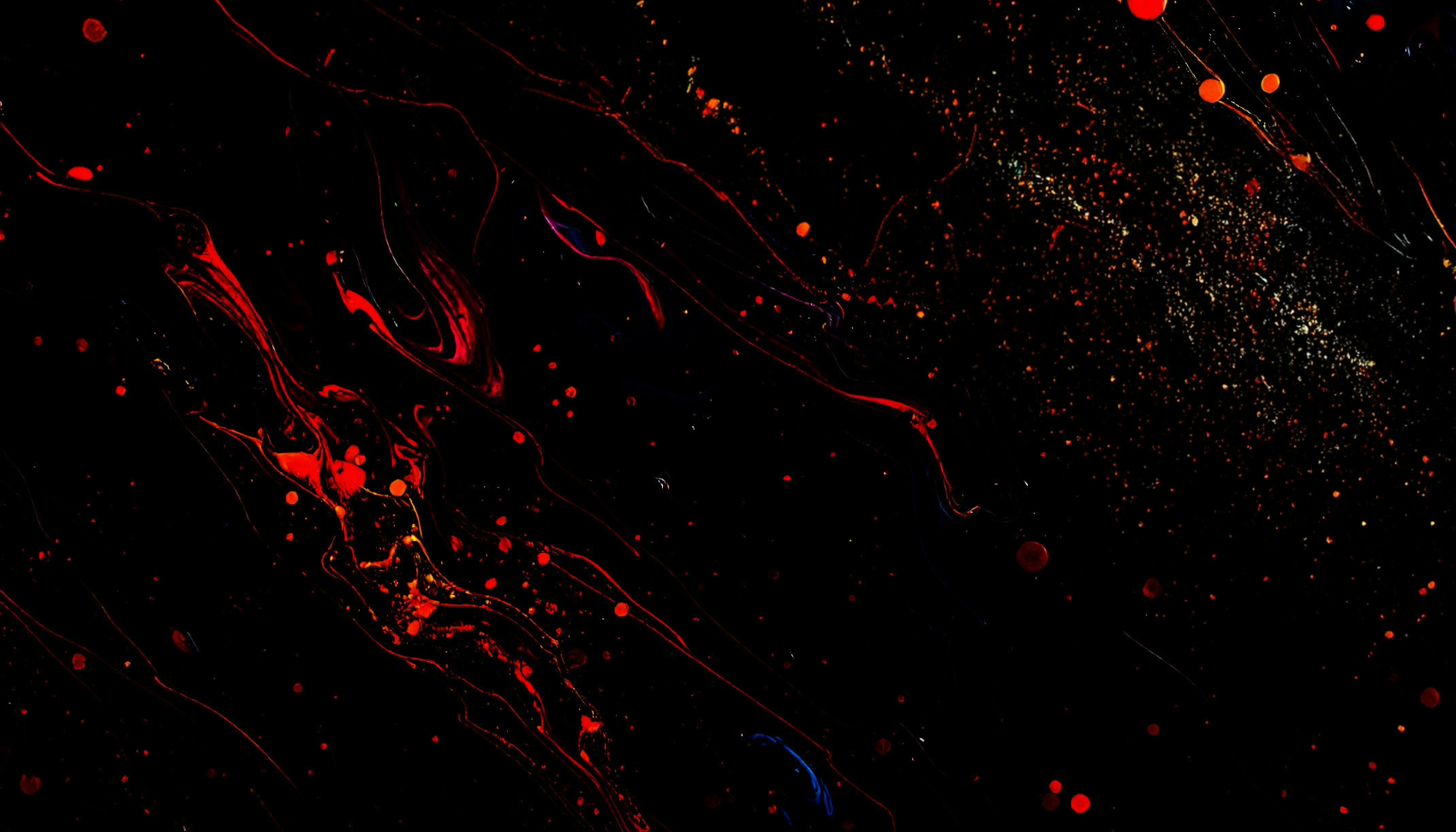
老化研究の羅針盤
AGING HALLMARKSは、老化現象を理解し、老化の根本的なメカニズムを特定するための枠組みとして、2013年にオランダの研究者チームによって生み出されました。
これは生物が年を取ると、身体的な機能や能力が低下し、様々な疾患や病気のリスクが増加するという普遍的な現象です。ヒトや他の生物は、加齢に伴う機能の低下を遅らせたり、疾患の発症を予防したりするために、老化メカニズムを理解する必要があります。そのために、研究者や科学者が共通の基盤として使用できるようAGING HALLMARKSが提案されました。

10年の進化
オランダの研究者チームは、老化の根本的なメカニズムが、9つの相互に関連するホールマーク(特徴)によって説明されると主張しました。これらのホールマークには、細胞老化、細胞内の異常なタンパク質の蓄積、エネルギー代謝の低下、炎症の増加などが含まれています。
そして、2023年にAGING HALLMARKSをアップデート。10年間でさらに蓄積された老化研究の成果を元に12種類の要因で定義されることになりました。
この枠組みは、老化の理解を深め、老化プロセスに関与するメカニズムを特定し、将来的には老化の遅延や予防のための介入策を開発するために使用されることが期待されます。AGING HALLMARKSは、老化研究の分野で広く受け入れられ、老化の理解に向けた重要なマイルストーンとなっています。